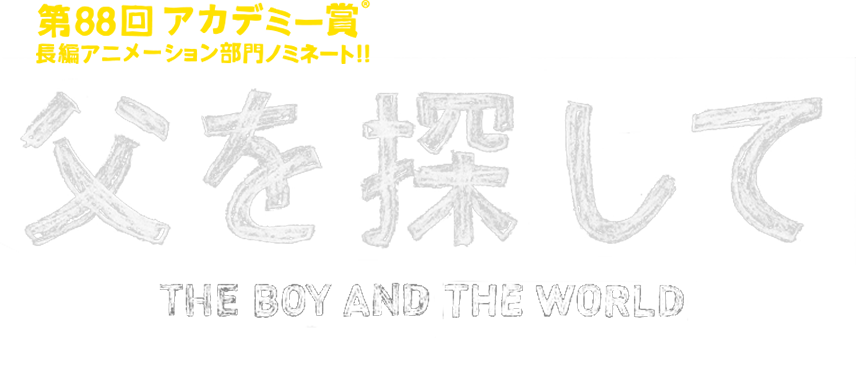デジタル技術の発達と浸透が個人作家たちに長編制作の道筋を拓いたこと、ヨーロッパを中心とした制作助成金のシステムがドキュメンタリーやマンガをはじめとする隣接分野の才能や個性あるアニメーション作家にチャンスを与えたこと、いくつかの地域においてアニメーション産業が新たに勃興しつつあること……そういった様々な背景に起因して、圧倒的な産業規模を誇るアメリカの一強は変わらないものの、それに次ぐ勢力が世界各地に現れてくるようになった。イラン出身のマルジャン・サトラピ(『ペルセポリス』)や、イスラエルのアリ・フォルマン(『戦場でワルツを』)の名前がまずは真っ先に挙がってくるだろう。ドン・ハーツフェルト(『きっと全て大丈夫』)やクリス・サリバン(『コンシューミング・スピリッツ』)などアメリカのインディペンデント分野の活況も目立っている。フランスはいまや継続的に優れた長編を生み出す場となった。『はちみつ色のユン』などドキュメンタリーとのつながりも見逃せない。近年でいえば、アイルランドのトム・ムーア(『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』)やルーマニアのアンカ・ダミアン(『マジック・マウンテン』)が、これまでの定番とは一味も二味も違う作品を生み出しはじめている。

ブラジルの現実を鮮やかに切り取る『父を探して』は、これら長編アニメーションの新潮流のひとつの傾向に則っている。その傾向が何かといえば、作り手の属する国・地域の現実に根ざし、キャラクター・登場人物たちの実際の息遣いが感じられそうになるほど、その土地で生きる人々に肉薄する物語を語ることである。
それは、過去より連綿と続く非主流・インディペンデント長編アニメーション作品の歴史の系譜に沿いつつ、そのアップデートを図る作業であったともいえる。アブレウが影響を公言するルネ・ラルーの『ファンタスティック・プラネット』や宮崎駿・高畑勲のアニメーション、もしくは宮崎や高畑にとってのアニメーションの原風景となったポール・グリモー『やぶにらみの暴君(王と鳥)』……これらの作家の作品においては、美麗なアニメーション技術の背後に、常に社会に対する言及や批判があった。寓話の形式を借りて、私たちが生きる世界の見取り図を観客へと突きつけようとする態度である。
『父を探して』にも、その種の寓話性は見て取れる。作品の原題は「少年と世界」。少年が対峙する世界の現実の描写のうちには、人々を抑圧する社会に対する作者の厳しい視線を間違いなく感じることができる。
ただし、『父を探して』には、これらの作品との大きな違いもある。先人たちの作品が、象徴的な図式のなかで世界の「全体像」を示そうとしていた一方(たとえば、『やぶにらみの暴君』でいう聳え立つ城と地下の人々の垂直構図)、『父を探して』が語るのは、あくまでも少年の目が捉えた世界の「断片」の姿でしかない。少年が旅をすればするほど、世界は全貌を示すどころかどんどんと広大になっていき、少年の存在のちっぽけさだけが浮き彫りになっていくのだ。
『父を探して』において、少年は世界に何の影響も与えることがない。多くの長編アニメーション映画において、主人公たちは「特別な」存在で、世界になんらかの変容をもたらすキーマンとなる。ある意味において、世界の中心の位置を占めているともいえる。一方で、『父を探して』において、世界は強固にそびえ立ったままで、戦争も、破壊も、貧困も、みなを苦しめるなにもかもが終わることがない。少年は、特別でもなんでもなく、世界の端っこにぽつりと存在するにすぎない。

かつてのアニメーションがシンプルなキャラクター造形を行うとき、その多くは、人間のある種の側面(強欲だったり、愚かさだったり…)を誇張して風刺することが多かった。しかし、『父を探して』のシンプルな造形デザインは、ナイーブさ、曖昧さ、ぼんやりとした感じを残し、傷つきやすくて、たゆたうようで、そのときごとに印象を変えていく。そのシンプルな描線は、一義的であることはなく、常に流転する――まるで、この世界のなかで、決して「特別」ではなく「普通」に生きる匿名的な私たちの存在や感情のありかたを丸ごとに捉えようとするかのように。だからこそ、棒線画に近いスタイルでありながら、『父を探して』の登場人物たちの奥底には、鮮烈な血流や脈動を感じることができる。少年の存在は、身近で、生きたものとなる。匿名化された私たちの生を、鮮やかにすくいとるのだ。
『父を探して』が迎えるこの結末を、あなたはどう捉えるだろう? 安らぎなのか、悲しみなのか。『父を探して』が描くのは、きわめて平凡で、世界を何も変えることのない匿名の人生だ。本当であれば物語として取り上げる価値もないかもしれないものである。だが、人間へと肉薄する『父を探して』は、そういったちっぽけな生に対して、あえて物語を紡ぎ出そうとしているように思える。この少年のような生は、これまでも、これからもずっと、いろいろな場所で延々と続いていくのだから、せめてそこに意味を与えようとするかのように思える。
だから、『父を探して』は限りなく優しい作品なのだ。なぜならば、懸命に生きられていくものの、誰にも気づかれることなく密やかに終わっていくなんでもない生があるとして、それを一本の長編として仕立てあげることによって、わたしたちひとりひとりの生を意味あるものとして祝福し、最終的な休息と安堵の場までをも与えようとするのだから。