




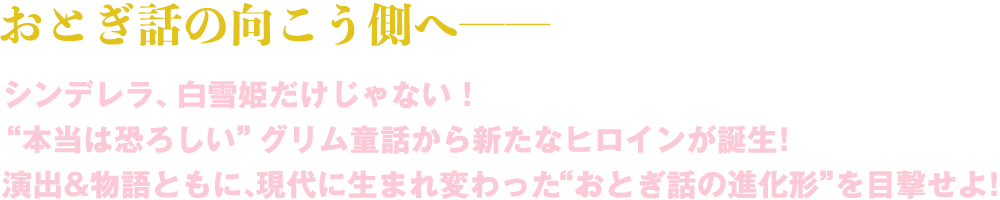
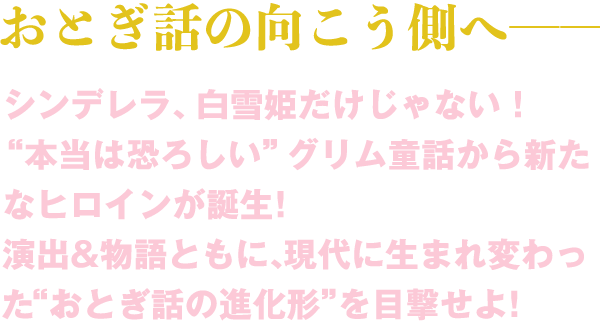
19世紀初頭にグリム兄弟によって書かれたドイツの民話集「グリム童話」は、160以上の言語に翻訳され聖書に並ぶといわれるほど世界中で読み継がれてきた。だが、オリジナル版には多くの残酷な場面や性的な事柄が含まれており、“本当は恐ろしい“童話として、日本でも大人向けに長年注目を集めてきた。
本作は「グリム童話」に初版から収録されている民話「手なしむすめ」を、新たによみがえらせた傑作アニメーションだ。ヒロインの少女は悪魔の企みで両腕を奪われ、数奇な運命に翻弄されながらも、不思議な精霊の力にも守られて、自分だけの幸せを見出していく。
ヒロインの生命力にあふれ、しなやかな生き方を、現代的な視点で描くのはフランスのセバスチャン・ローデンバック監督だ。故・高畑勲監督の実験精神に敬意を表する監督は、本作で驚嘆の作画技法「クリプトキノグラフィー」を用い、長編でありながら全ての作画をたったひとりで手がけた。まるで線そのものが命を持ち、呼吸するかのような美しい映像に、思わず息を呑む。そして、王子との結婚の先に少女を待ち受ける思いがけない物語の展開は、原作とは異なる監督ならではのラストへと観客を誘っていくだろう。
本作は「グリム童話」に初版から収録されている民話「手なしむすめ」を、新たによみがえらせた傑作アニメーションだ。ヒロインの少女は悪魔の企みで両腕を奪われ、数奇な運命に翻弄されながらも、不思議な精霊の力にも守られて、自分だけの幸せを見出していく。
ヒロインの生命力にあふれ、しなやかな生き方を、現代的な視点で描くのはフランスのセバスチャン・ローデンバック監督だ。故・高畑勲監督の実験精神に敬意を表する監督は、本作で驚嘆の作画技法「クリプトキノグラフィー」を用い、長編でありながら全ての作画をたったひとりで手がけた。まるで線そのものが命を持ち、呼吸するかのような美しい映像に、思わず息を呑む。そして、王子との結婚の先に少女を待ち受ける思いがけない物語の展開は、原作とは異なる監督ならではのラストへと観客を誘っていくだろう。



水車小屋に暮らす父・母・娘の三人家族。水も枯れ果て、日々の食料にも困っている。ある日、父親の元に悪魔が現れる。「水車の裏にあるもの」と引き換えに、黄金を与えようというのだ。林檎の木だと思い込んだ父親は取引に応じ、枯れていた川に黄金が流れ込む。生活が変わる。
しかし悪魔が求めたのはその林檎の木に登っていたもの――彼の一人娘だった。富を失いたくない父親は、悪魔に追い詰められる。母親は野犬に食われて死んだ。娘は窮地の父親を救うため、自分の両腕を切り落とさせる。父親との関係性にもウンザリした娘は家を出る。父親は絶望し命を断つ。
しかし悪魔が求めたのはその林檎の木に登っていたもの――彼の一人娘だった。富を失いたくない父親は、悪魔に追い詰められる。母親は野犬に食われて死んだ。娘は窮地の父親を救うため、自分の両腕を切り落とさせる。父親との関係性にもウンザリした娘は家を出る。父親は絶望し命を断つ。

腕を失った少女は雨のなか森を行く。生きるために梨を食べようとするが、足を滑らし、川に落ちる。そこで彼女を待つのは川の精だった。川の精は語る――梨は王子のものであること、少女がそれを求めることは運命なのだという。王宮に足を踏み入れる少女を、王子は受け入れ、后とする。結婚式で少女は金色の義手を得る。充分な食料と愛。何一つ不自由ない生活。子供も授かった。
だが、戦争が始まった。王子は戦いに出る。そして悪魔が暗躍する。出産の知らせの手紙を書き換え、化物の赤子が生まれたと王様に信じさせる。さらには、庭師を騙し、母親もろとも殺すよう仕向ける。少女は生まれたばかりの赤子を抱え、王宮から逃げ出す。庭師から密かに渡された、新世界からの魔法の種を懐に入れて。
だが、戦争が始まった。王子は戦いに出る。そして悪魔が暗躍する。出産の知らせの手紙を書き換え、化物の赤子が生まれたと王様に信じさせる。さらには、庭師を騙し、母親もろとも殺すよう仕向ける。少女は生まれたばかりの赤子を抱え、王宮から逃げ出す。庭師から密かに渡された、新世界からの魔法の種を懐に入れて。

赤子を抱え様々な地を転々とする少女は、川の精に導かれながら、安住の地を見つけだす。実用性に欠いた黄金の義手は捨て去り、自らの腕で血を流しながらその地を耕し、種を植え、自給自足の生活をする。一方戦争に敗れた王子が城へと戻ってくる。悪魔の策略に気づき、妻と息子を探すため再び旅に出る。
数年が経った。少女は母となり、息子は元気に育った。旅を続ける王子はいつしか妻の生家に辿り着く。そこにあるのは自ら命を断った父親らしき男の姿、黄金の川のほとりに流れ着いた義手、そして、白骨化した両腕。その骨のひとかけらを王子はそっと飲み込む。悪魔はまだ諦めない。ついに王子が愛する妻と息子と再会するなか、いまや母親となった少女の魂をめぐる、最後の戦いが始まる。その果てに、少女とその家族が最後に向かう場所は、はたして?
数年が経った。少女は母となり、息子は元気に育った。旅を続ける王子はいつしか妻の生家に辿り着く。そこにあるのは自ら命を断った父親らしき男の姿、黄金の川のほとりに流れ着いた義手、そして、白骨化した両腕。その骨のひとかけらを王子はそっと飲み込む。悪魔はまだ諦めない。ついに王子が愛する妻と息子と再会するなか、いまや母親となった少女の魂をめぐる、最後の戦いが始まる。その果てに、少女とその家族が最後に向かう場所は、はたして?

グリム童話「手なし娘」との出会い、動きの重要性
――なぜ数あるグリム童話の中からこの物語を選んだのですか。
ローデンバックこの物語を元にしたオリヴィエ・ピィの演劇作品がありまして、それをアニメーションにしないかという提案がプロデューサーからありました。そこで初めて原作を読んだのですが、とても現代的で、自分自身に強いインスピレーションを与えてくれました。物語としても非常に普遍的だと感じました。人間個人が社会のなかでいかに存在しうるかということが描かれている。ヨーロッパでも決して有名な話ではないのですが、とにかく強い作品だと思いました。
提案された企画自体は数年かけても資金が集まらず、頓挫しました。しかしこの童話自体を作品にしたいという気持ちはずっと残りました。どうすれば実現できるのか……例えばバンドデシネにすることも考えましたし、実写化も考えました。その過程において、『手をなくした少女』として完成に至るまで、自分自身と格闘していたようなところがあったと思います。なので、この作品の物語自体、自分自身の軌跡に似ている。少女の手が切られるところは元々の作品の企画が頓挫したことにあたり、しかし自分自身で種を撒き、その種が庭で育っていった……作品が育っていくその過程が、この映画の物語になっているのです。
――全体的に、軌跡(トラジェクトワール)という言葉がこの作品のテーマであるよう思います。イメージの変容のなかで一番感動したもののひとつは、形が消えて、また一定時間するとフッと現れて……というところ。形が見えないとしても、物体が軌跡を描いているということがわりとわかってしまうところです。消える運動という発想はどこから来たのでしょう?
ローデンバックこの映画の物語は軌跡でもあり、同時に動きであります。というのも、娘はあちこちいろいろな場所を移動するわけです。水車小屋から出て、城に辿り着き、そして城を出る。さらにいえば、動きの物語でありつつ、存在についての物語でもある。ご指摘の技術は、その意味において非常に興味深いものになると思います。物語をそのまま表しているわけですから。その人物が存在するのかしないのか、その状況をそのままビジュアルで見せることができる。
先ほども言ったように、アニメーションは肉体を描けません。そこにあるのは、線と色だけです。でもこの技術によって、少なくとも、存在することと存在しないことの間を描き出せる。ちょっと理論的すぎる話かもしれませんが、物語の主題と形式、そしてフォルムが、動きのうちでひとつに融合しているわけです。
少女を描く「水」
――主役である少女のキャラクターが面白いです。彼女はあたかも、リンゴの木の上をテリトリーとしている動物のようですね。木の上からおしっこをするシーンも衝撃的でした。ほかにも、ツバを吐いたりとか、子供が生まれたときの授乳もそうなのですが、液体を介した身体性を強調しているところが、この作品の1つの生々しい特徴だと思いました。
ローデンバック液体は、身体を描くときに重要でした。身体性は、アニメーションを作るときに常に興味を引かれるテーマです。というのも、アニメーションには、身体が根本的に存在のしようがないからです。身体は、描かれたものを通じて、なんらかの媒介を通じて、ようやく表象される。身体そのものを描くことはできない。だからこそ私は、身体をアニメーションでどのように扱うのかについて、興味を持ちつづけてきたのです。
少女は映画の中で泣きます。おしっこもします。おしっこについては、原作にはありませんでした。授乳もそうです。授乳という行為は、液体のかかわる肉体的な行為の中でも喜ばしいものだと思いますが、そういう行為を描くことが、身体を描くことにつながる。液体は、身体を描くため(身体を観客に感じさせるため)に必要だったのです。映像のなかで肉体をどう描くか。この作品では、主人公の少女が手という肉体の一部を失うところから始まりますが、そのような肉体をどう描くのか? それが作品にとって重要だということは理解していました。
少女は映画の中で泣きます。おしっこもします。おしっこについては、原作にはありませんでした。授乳もそうです。授乳という行為は、液体のかかわる肉体的な行為の中でも喜ばしいものだと思いますが、そういう行為を描くことが、身体を描くことにつながる。液体は、身体を描くため(身体を観客に感じさせるため)に必要だったのです。映像のなかで肉体をどう描くか。この作品では、主人公の少女が手という肉体の一部を失うところから始まりますが、そのような肉体をどう描くのか? それが作品にとって重要だということは理解していました。
――水に関していえば、フランス語の水(オー)と金(オル)は発音が近い。でも、意味合いとしては全然ちがう。『手をなくした少女』では、金が水のように流れ、それで富を得るわけですが、その金には「汚らしい」という言葉が与えられる。
ローデンバック水はこの作品にとって非常に重要です。元々のグリム童話の原作には水は登場しません。風車は出てくるんですが。原作ではどちらかといえば風のイメージが強いのですが、私はこれを水車小屋にしました。というのも、結局、水の流れというもの、水が辿る軌跡が少女の辿る道のりと一致していく……そういうことをこの作品の中で描きたいと思っていたからです。水はあるときには、せき止め、流れを止める。一方で、流れることで彼女を助けるものにもなりうる……そういうことを描くために、私にとって、水が必要でした。
水の女神も元の原作には出てきません。原作はキリスト教色が非常に強く、いわゆる守護天使がでてきて、川を渡るようなかたちで橋を掛けるんですね。それによって少女は橋を渡ることができ、梨を食べることができる。それが原作の元々の話でした。
『手をなくした少女』を作るうえで、宗教的な側面は取り除きたいと思いました。宗教的なものではなく、自然をそこに現すということが非常に重要でした。なので最初は川を渡るときに鹿を登場させて、それに乗って渡るということを考えました。しかし、すべての作画を行うのは自分であり、鹿を描くのは技術的にあまりにも難しいということに気づきました。
では、どのように彼女に橋を渡らせればよいのか? まったくわからないまま、作画を続けました。少女は、足を、川に一歩、また一歩と踏み入れていく……少しずつ進んでいく。そして、一生懸命泳ごうとする。でも、彼女は絶対向こう岸には辿り着けない。彼女もそのことは分かっていました。でも、だからといって、どうしたらいいかは分からない……結局、川底まで沈んでしまう。そのときようやく、水の女神が彼女を手で受け止め、助けるというアイデアを思いつきました。だから、水の女神という存在は、即興によるものなのです。金が金のように流れることも、元々の発想にはなかった。これもまた、作りながら思いついたことでした。
水の女神も元の原作には出てきません。原作はキリスト教色が非常に強く、いわゆる守護天使がでてきて、川を渡るようなかたちで橋を掛けるんですね。それによって少女は橋を渡ることができ、梨を食べることができる。それが原作の元々の話でした。
『手をなくした少女』を作るうえで、宗教的な側面は取り除きたいと思いました。宗教的なものではなく、自然をそこに現すということが非常に重要でした。なので最初は川を渡るときに鹿を登場させて、それに乗って渡るということを考えました。しかし、すべての作画を行うのは自分であり、鹿を描くのは技術的にあまりにも難しいということに気づきました。
では、どのように彼女に橋を渡らせればよいのか? まったくわからないまま、作画を続けました。少女は、足を、川に一歩、また一歩と踏み入れていく……少しずつ進んでいく。そして、一生懸命泳ごうとする。でも、彼女は絶対向こう岸には辿り着けない。彼女もそのことは分かっていました。でも、だからといって、どうしたらいいかは分からない……結局、川底まで沈んでしまう。そのときようやく、水の女神が彼女を手で受け止め、助けるというアイデアを思いつきました。だから、水の女神という存在は、即興によるものなのです。金が金のように流れることも、元々の発想にはなかった。これもまた、作りながら思いついたことでした。



王子や庭師たち
――『手をなくした少女』の登場人物の配置は非常に現代的だと思います。少女と両親――父親と母親――の関係も興味深いですが、私が特に惹かれたのは、庭師の存在です。
ローデンバックこの原作が非常に現代的であるのは、少女と王子の結婚が、物語の結末ではなく真ん中にあり、ある種の官能的な瞬間としてのみ描かれていることです。城の中の生活も、幸せな時間としては描かれていない。城の生活は、水車小屋での生活と同質なのです。もちろん、人間や感情の配置が全く同じというわけではない。たとえば、王子が少女と結婚し、愛し、欲望をすることは正当化できるが、一方で、水車小屋での父親には、それが正当化される理由はない。父親は子供のように育ってしまった人であり、娘が小さい女の子から思春期に移り変わっていく過程のなかで、近親相姦的な要素が入り込んでくるわけです。
グリム童話には様々なバージョンが存在し、庭師はそのすべてに登場するわけではありません。しかし、彼は重要な人物だと思いました。城の中で、少女はただ一人の女性です。庭師は男性で、おそらくは少女に恋をしている。そして少女に敬意を示しつつ、彼女を助ける。そういう存在が必要だと感じました。
一方、水車小屋には女性的な要素が2つあります。1つは母親です。母親は娘を助けようとして、結局は助けられない。さらにもう1つ女性的な要素として川(の女神)がいる。これらに変わる要素として、城の中での生活における優しさ、柔和さのある存在として、庭師が必要でした。男性であって、なおかつ女性的な性質を持つ存在です。他の男性とは違います。たとえば王子は彼女を愛しながらも、結局父親と同じように彼女を閉じ込める。しかも、金の檻にです。たとえ彼女を愛していて、情熱があったとしても、非常に不器用な存在なのです。
こんなふうに、城の中での生活と水車小屋での生活は、ある種の鏡像関係になっています。王子の存在は、水車小屋での父親との関係に対応する。城のなかでの庭師は、水車小屋での母親や水の女神に対応する。庭師を優しい存在として描きたかったのは、城の生活がお金はあっても、少女にとって非常に過酷で幸せではない場所だったからです。
グリム童話には様々なバージョンが存在し、庭師はそのすべてに登場するわけではありません。しかし、彼は重要な人物だと思いました。城の中で、少女はただ一人の女性です。庭師は男性で、おそらくは少女に恋をしている。そして少女に敬意を示しつつ、彼女を助ける。そういう存在が必要だと感じました。
一方、水車小屋には女性的な要素が2つあります。1つは母親です。母親は娘を助けようとして、結局は助けられない。さらにもう1つ女性的な要素として川(の女神)がいる。これらに変わる要素として、城の中での生活における優しさ、柔和さのある存在として、庭師が必要でした。男性であって、なおかつ女性的な性質を持つ存在です。他の男性とは違います。たとえば王子は彼女を愛しながらも、結局父親と同じように彼女を閉じ込める。しかも、金の檻にです。たとえ彼女を愛していて、情熱があったとしても、非常に不器用な存在なのです。
こんなふうに、城の中での生活と水車小屋での生活は、ある種の鏡像関係になっています。王子の存在は、水車小屋での父親との関係に対応する。城のなかでの庭師は、水車小屋での母親や水の女神に対応する。庭師を優しい存在として描きたかったのは、城の生活がお金はあっても、少女にとって非常に過酷で幸せではない場所だったからです。
――しかし、老いてからの王子については決定的な違いがありますね。王子が自らの最初の役割を反省し、少女を探し求める。さらにそこで庭師が王子を助けるという役割を果たします。庭師の優しさが、少女だけではなく王子に対しても機能するところがとても興味深いです。
ローデンバックおっしゃる通りだと思います。さきほど鏡像関係にあると申し上げましたのは、あくまで娘が城にいた時までです。娘が城から出てしまったあと、この鏡像関係は成立しません。物語はあくまで、少女の軌跡を描くものです。少女がこの世界の中において自分の居場所を見つけるまでの軌跡を描くことが、この映画の物語です。
それは、空間だけではなく、同時に、彼女が時間を見つけるということでもあります。どういうことかといえば、彼女が成長するということです。彼女が植えた種が木々や植物として成長するのと同じように、彼女自身も、自分が成長する時間を必要としている。それを彼女が見出すのも、この物語だと思います。それに、これは王子の物語でもあります。王子は確かに紋切り型のクリシェとして描かれています。つまり、「男であるから戦争にいかなくてはいけない」「戦争に行って成長してくる」というある種のステレオタイプな物語に基づいて王子は描かれる。でも、結局老いて戻ってくると、前とは違った姿でそこに存在するようになる。
それは、空間だけではなく、同時に、彼女が時間を見つけるということでもあります。どういうことかといえば、彼女が成長するということです。彼女が植えた種が木々や植物として成長するのと同じように、彼女自身も、自分が成長する時間を必要としている。それを彼女が見出すのも、この物語だと思います。それに、これは王子の物語でもあります。王子は確かに紋切り型のクリシェとして描かれています。つまり、「男であるから戦争にいかなくてはいけない」「戦争に行って成長してくる」というある種のステレオタイプな物語に基づいて王子は描かれる。でも、結局老いて戻ってくると、前とは違った姿でそこに存在するようになる。
――極論すれば、父親がいなくても、少女と息子は穏やかに暮らしていける。しかし少女は自分の夫とのあいだに新たな関係を作り直していく。そこにこの物語の素晴らしさを見ました。老いた王子を庭師がサポートし、そこから王子にとって第二の旅が始まるところに、この物語の伏線的魅力があるのではないかと思います。親子3人は最後、第三の場所へと旅立っていく。非常に感動しました。
ローデンバック私がこの物語を普遍的なものだと考えるのは、それぞれが自分の世界において、自分の居場所を見つける物語だからです。他人との関係性を得る為に、まず自分の居場所を見つける。そしてようやく、他人との関係性を得る。この物語が普遍的だと思う理由はその部分です。自分の居場所を見つけるための過程のなかに、両親の存在がたとえばある。この物語ではまず家庭という場所で、少女は一人で立ち、一人で自分の居場所を見つける。最初は、自分の居場所を見つけるために他人を必要とするわけです。
その後、娘は王子と城を必要とします。王子がいることで、一人になるための自分の居場所を得る。王子はそのために必要な存在にすぎません。そこで1人になることに成功した少女は、城から出ていきます。そして最後に、もう一度王子と出会いなおす。ここには、必要と欲望の2つの違う欲求があります。居場所を見つける為に他人を必要とするということと、自分の居場所を得たうえで、もう1度他人を欲すること。他人と出会いたい、他人と関係を結びたいと欲望。その両方を描くからこそ、この物語は普遍的だと思います。2人は最終的に関係を作り直します。
グリム童話の原作では、最後に城に戻るんですね、新たにどこかに行くのではなく、城に戻って、2人が二度目の結婚をして終わる。でも私は、この結末を現代的なままにしたかった。原作の最後で二人が交わす会話は、こんな感じです――私たちは元のように戻った。でもここは私の場所で、あなたの場所ではないし、私はあなたの場所に戻りたくもない。私たち2人の場所に戻りたい。この考えを自分の作品の中には残したいと思いました。だから最後、2人は城に戻らない。2人の場所を見つけるために、どこかへと旅立つというラストにしたのです。
その後、娘は王子と城を必要とします。王子がいることで、一人になるための自分の居場所を得る。王子はそのために必要な存在にすぎません。そこで1人になることに成功した少女は、城から出ていきます。そして最後に、もう一度王子と出会いなおす。ここには、必要と欲望の2つの違う欲求があります。居場所を見つける為に他人を必要とするということと、自分の居場所を得たうえで、もう1度他人を欲すること。他人と出会いたい、他人と関係を結びたいと欲望。その両方を描くからこそ、この物語は普遍的だと思います。2人は最終的に関係を作り直します。
グリム童話の原作では、最後に城に戻るんですね、新たにどこかに行くのではなく、城に戻って、2人が二度目の結婚をして終わる。でも私は、この結末を現代的なままにしたかった。原作の最後で二人が交わす会話は、こんな感じです――私たちは元のように戻った。でもここは私の場所で、あなたの場所ではないし、私はあなたの場所に戻りたくもない。私たち2人の場所に戻りたい。この考えを自分の作品の中には残したいと思いました。だから最後、2人は城に戻らない。2人の場所を見つけるために、どこかへと旅立つというラストにしたのです。


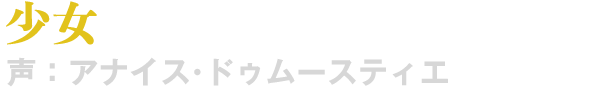
1987年生まれ。7歳から演劇を学び、13歳でミヒャエル・ハネケ『タイム・オブ・ザ・ウルフ』(03)に出演。フランソワ・オゾン「彼は秘密の女ともだち」(14)に主演、セザール賞有望若手女優賞にノミネートされるなど、フランスの新鋭スターとして期待されている。
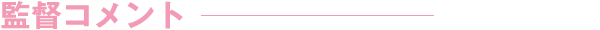
「彼女がスタジオに来た初日、最初に声を録音した瞬間は、感動的でした。長年ずっと声のない状態で、この作品を作り続けていたので……まず、少女が呼吸する音から撮り始めました。それがアニメーションについた瞬間、少女の存在を初めて感じました。悪魔との対決のシーンで彼女は叫びますが、そのとき彼女は妊娠していた。大丈夫かと聞きましたが、平気だと言ってくれました。録音は素晴らしかったのですが、結果的に、出産予定日よりも2週間早く子供は生まれてしまいました(笑)。ちなみにその父親は、ジェレミー・エルカイム、王子の声優です。」


1978年生まれ。『わたしたちの宣戦布告』(11)では主演と脚本を担当。脚本はセザール賞にノミネートされるなど幅広く活躍する。本作では王子の青年期と壮年期という2つの年代を演じ分けている。
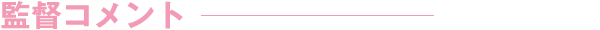
「王子については、最初から彼を想定していました。王子は、若い声も年老いた声も演じなくてはいけない。それができるのは彼だけだろうと。

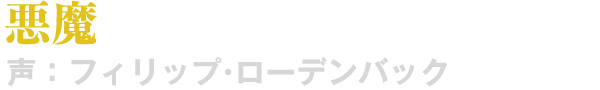
1936年生まれ。エリック・ロメールやアルノー・デプレシャンなどヌーヴェルヴァーグの多くの映画作品に出演し、フランソワ・トリュフォーの遺作『日曜日が待ち遠しい!』では主役を演じている。
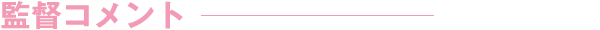
「実はフィリップと自分は遠い親戚です。 どちらかとえば端役での出演が多いのですが、フランスの映画史・演劇史のなかでは非常に重要な役者です。 」


1962年生まれ。ミシェル・ゴンドリー監督作品に多く出演する。『恋愛睡眠のすすめ』(07)、『グッバイ、サマー』(16)など。
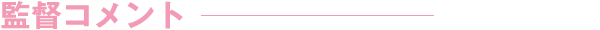
「庭師と川の女神は、少女の友人かつ彼女を救うという二重の存在ゆえ、2つのニュアンスを持つ声が必要でした。そこで女神はルーマニア人エリナ・レーヴェンソン、庭師はロシア人のサッシャ・ブルドに依頼しました。フランス語と母語の両者のニュアンスを持たせることで、外からの声としても響くようにしたかった。サッシャには女性的な声を出すようお願いしました。優しさの感覚が欲しかったのです。」


1963年生まれ。映画、舞台で活躍する。フランスのカルト的テレビドラマ「Les Deschiens」など。
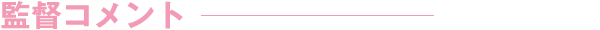
「父親の声は私にとって一番難しかった。キャラクターがはっきりとした顔を持つからです。もしくは、彼が弱いからかもしれない。最初は違う俳優に頼んでいたのですが、最初の試写で声が聞き取れないという反応が多く、最終的にオリヴィエに頼みました。彼が弱さと強さの両方を表現できるからです。」


1944年生まれ。ジャン・ユスターシュ『ママと娼婦』(73)に出演し、マルグリット・デュラス作品でもモノローグを務める。2008年には彼女のドキュメンタリーも作られている。
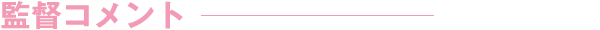
「フランソワーズ・ルブランは、才能に溢れています。自分自身のキャリアのために力強い選択ができるタイプの俳優で、それゆえに彼女を選びました。」



1973年、フランス北部に生まれる。国立高等装飾美術学校にてアニメーションを学び、現在そこで教えてもいる。『JOURNAL』(1998年、クレルモンフェラン映画祭でYouth賞を受賞)、『DES CALINS DANS LES CUISINES』(2004年、セザール賞の最終選考)、『REGARDER OANA』(2009年、アヌシーおよびクレルモンフェランに選出)、『VASCO』(2010年、カンヌ批評家週間で上映、2012年のセザール賞の最終選考)、『DAPHNÉ OU LA BELLE PLANTE』(2015年、シルヴァン・デロインと共同監督、エミール・レイノー賞受賞)、パリ国立オペラのウェブサイト用に作られた『VIBRATO』といった彼の作品は、数々の著名な映画祭で上映されている。『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』は初の長編作品で、グリム童話の短編を原作としている。
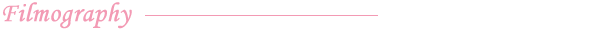
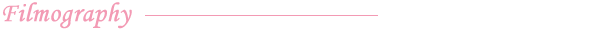
JOURNAL (1998)/DES CALINS DANS LES CUISINES (2004)/Morceau (2006)/REGARDER OANA(2009)/VASCO (2010)/XI. LA FORCE (2012)/Un accident de la chasse (2014)/DAPHNÉ OU LA BELLE PLANTE(2015)/OSN (2015)/OBET (2015)/Droit et Gauche (2015)/大人のためのグリム童話 手をなくした少女 La Jeune Fille sans mains(2016)/VIBRATO(2017)/Dominique A “Toute latitude”, “Aujourd’hui n’existe plus”, “Se décentrer”, “Cycle”(2018)/Linda veut du poulet !(in production)※現在製作中の二作目の長編



セバスチャン・ローデンバックは、いま、アニメーションがその歴史上初めて変革の時期を経験していると考えている。そして、自身の初長編作品である本作『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』が、その一角をなすものであるとも。
ローデンバックのキャリアは掴み難い。彼は常にアニメーションを作る人間として活動しつづけてきたが、自分自身を「アニメーション作家」であるとみなすことには、常に懐疑的であった。ローデンバックはそもそもバンド・デシネ作家になりたくて、国立高等装飾美術学校(ENSAD)に入学した。しかし、アニメーション専攻を立ち上げろと要求する学生たちの運動でいつの間にか陣頭に立たされて、そのまま一期生となってしまった。それならばと作った卒業制作の『日記』は、彼の日々の出来事を綴っていくもので、本人もその周囲も、あまり観たことがないタイプのアニメーションだと思った。そして、ローデンバックは、アニメーションには未踏のままに残された領域が広大にあることに気づき、社会に出た彼は、野生ともいえるその領域を探索することをキャリアとして選ぶことになる。
『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』以前にローデンバックが残した達成は、とても掴み難い。彼はアニメーションの可能性を信じているが、しかし現実的に作られているものはそれを活かしきっていないとも考えている。そんなローデンバックの短編作品におけるキャリアは、可能性を探る過程である。彼はアニメーション作家のなかで、高畑勲とノーマン・マクラレンをとりわけ好んでいるのだが、それは彼らが、作品ごとに必然性のある手法を選び、ひとつとして同じ作品を作らないからである。
ドキュメンタリー、砂絵、抽象、物語、実験……本作『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』にたどり着くまで、ローデンバックの短編作品群はとにかく多彩な顔を見せており、それは、あまりにも多彩すぎて、同一作家のものには思われないくらいである。実際、短編作家時代のローデンバックは映画祭シーンではそこまで認知度が高くなかった。専門家からしても、ローデンバックのスタイルというものを捕捉することが難しかったというのが、その理由だろう。(アヌシー国際アニメーション映画祭に作品が選出されたのも、本作が初めてのことだった。)
そんなふうにして経歴を重ねてきたローデンバックがたどり着いた初長編『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』は、長編作品としては異例のスタイルをもつものとなっている。長編でありながら作画をすべてひとりでやること……そのこと自体はいまや珍しくなくなった。しかし、人によっては未完成に思えてしまうようなデッサン調の絵柄によって全編が構成され、それでもなお、「実験的」であることが前面には出されず、ある種の大衆性を獲得しているというこの立ち位置は、おそらく前代未聞のものであろう。
本作はカンヌ映画祭でのプレミア上映からスタートして、世界中の映画祭で大きな評価を得ている。フランスでは子供向けにリリースされ、ヒットも飛ばしている。見慣れぬスタイルではあれど、受け入れられているのだ。『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』は、ローデンバックにとって、「長い短編」を作る試みでもあった――短編でしか可能でないはずの実験的で特異なスタイルを長編によって成立させることを試すという意味において。
そんな態度の本作がこれほどまでに世界的な支持を獲得しているのは、この「長い短編」のようなスタイルで作られた長編アニメーションが、世界中で増えつつあるからだ。トム・ムーア(『ブレンダンとケルズの秘密』『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』)、アレ・アブレウ(『父を探して』)、アルベルト・バスケス(『サイコノータス(日本未公開)』)……さらにはウェス・アンダーソンの人形アニメーション作品(『ファンタスティックMr.Fox』『犬ヶ島』)だったり、『この世界の片隅に』の片渕須直、さらには京都アニメーションの山田尚子ら、独自の世界を作り上げるタイプのアニメ作品もその列に含めてもいいかもしれない。これら「長い短編」としての長編作品は、アニメーション産業における既存の定型を否定し、監督=作家のパーソナルなスタイルを全面に押し出しつつも、大衆性を獲得する。これらの作品群が、本作のための着地点を準備したのだ。
ローデンバックはその象徴的な始まりを湯浅政明の初長編『マインド・ゲーム』に見ている。カリカチュアの効いた造形のドローイング、自然主義とは程遠い色使い、臆せず用いられる実写……変化するリアリティに応じて多彩なスタイルを組み合わせる本作は、日本以上に海外で影響力が強く、当時の若い作家たち(=現在活躍する中堅の作家たち)にそのあとを追わせた。『マインド・ゲーム』が何を教えたのかといえば、アニメーションにおいて、ビジュアルのスタイルはどんなものであってもよく、語られるべきものに従って変幻自在となってよい、ということである。それはつまり、ローデンバックが短編においてやってきたことでもある。湯浅政明が『夜明け告げるルーのうた』で世界最大のアヌシー国際アニメーション映画祭にてクリスタル(グランプリ)を獲得するその前年、『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』は審査員賞を受賞している。これら「長い短編」の作品はいまや、世界のアニメーションの新たなスタンダードとなっているのだ。
これら「長い短編」作品たちは、それぞれに必然的なスタイルを見つけ、これまでのアニメーションのあり方にヒビを入れ、新たな景色を見せ、可能性を発掘していく。では、『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』が見出したアニメーションの可能性、その「革新」とはなんだろうか? それは、広い余白と、強固な輪郭もはっきりとした顔立ちも持たない抽象的なキャラクターを活用することで、寓話としてアニメーションを機能させることである。少女、悪魔、王子、庭師、水の精……本作では、誰もが固有名詞の名前を持たない。「クリプトキノグラフィー」を随所に用いながら走るように描かれた筆絵のアニメーションは、動的に姿を変容させ、とらえどころがない。少女は主人公であるにもかかわらず、顔がはっきりしない。作品は全体として、曖昧で流動的な印象を持ったままに揺れ動くのだ。
その「曖昧さ」は何をもたらすのか? ローデンバックは本作の日本公開のために二度来日し、様々な媒体からの取材を受けたが、そこで日本人の記者から「少女が東洋人に見える」という指摘を受けるたび、苦笑していた。なぜなら、彼にとっては、少女はブロンドの白人だったからだ。これが意味するのは、造形上の失敗ではない。抽象度の高いビジュアルが、作品を観る人によって、それぞれ違ったイメージとして読み取ることを許容する、ということである。
観る人によって印象を変える、その揺らめき動きつづける感覚こそが、本作には必要だった。ローデンバックはグリム童話の原作「手なし娘」に、今でも通用するような普遍性を見出した。少女の辿る道、王子の成長、父親の葛藤といったものすべてに、自らの人生のどこかしらの部分を読み込んだ。おそらく、観客である私たちもまたそうだろう。画面のなかでうごめくイメージが、まるでロールシャッハテストのように、自分の人生を映す動的な鏡として、何かを読み込ませる。そして、感情を強く、深く揺さぶる。普段名前をつけることができないあの気持の揺れがイメージとシンクロする。何も確かなものを示さないがゆえに、無限に複雑で機微に富んだ感情を、本作のアニメーションは、豊かな井戸のように汲み取りつづけることを許す。
そのような作品のあり方にとってのキーワードとして、ローデンバックは「謎」という言葉を挙げる。それは、解釈にブレがなく、ひと目で見てわかる、一般的なアニメーションのあり方とは大きく異なる。フランスで本作は子供向けにリリースされたが、しかし本作は「子供にかしづく」ようなものではないという。「子供だからこれくらいでいいだろう」というものでもない。子供が見たこともない世界に背伸びをして、それによって何かを未知なるものを読み込めるものにしているのだという。本作は謎を謎のままに残す。そこから何を受け取るべきなのか、何を見出すべきなのか、本作は明確な答えを用意しない。その答えはあくまで、自分で見出すしかない。答え合わせもできない。だから、本作を観ることは、まるで冒険のようでもある。筆者が本作を初めて観たとき、とても勇敢な作品だと思った。誰も作ったことがないような表現を、長編アニメーションという場で臆することなく行う、まったくブレるところのない作品に見えたからだ。私は自分の道を行き、曖昧で流動的な未踏の領域を切り開いていくが、きっとその場所から、あなたもなにかを汲み取るだろう?という、観客に対する信頼を感じたからだ。
少女は常に移動する。最初はやむなき事情だったが、最後には自分の意志で、未踏の地へと飛び立つことを選ぶ。本作を観るとき、この変化の過程を、観客もまた体験するはずだ。未踏の表現が見せる、誰もまだ確かな答えを持たない「野生の」場所への飛翔。他の数多くの「革新」たちとともに、本作はアニメーションの野生を切り開く。そして、その先に、自分だけの場所を探すことを促すのだ。
ローデンバックのキャリアは掴み難い。彼は常にアニメーションを作る人間として活動しつづけてきたが、自分自身を「アニメーション作家」であるとみなすことには、常に懐疑的であった。ローデンバックはそもそもバンド・デシネ作家になりたくて、国立高等装飾美術学校(ENSAD)に入学した。しかし、アニメーション専攻を立ち上げろと要求する学生たちの運動でいつの間にか陣頭に立たされて、そのまま一期生となってしまった。それならばと作った卒業制作の『日記』は、彼の日々の出来事を綴っていくもので、本人もその周囲も、あまり観たことがないタイプのアニメーションだと思った。そして、ローデンバックは、アニメーションには未踏のままに残された領域が広大にあることに気づき、社会に出た彼は、野生ともいえるその領域を探索することをキャリアとして選ぶことになる。
『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』以前にローデンバックが残した達成は、とても掴み難い。彼はアニメーションの可能性を信じているが、しかし現実的に作られているものはそれを活かしきっていないとも考えている。そんなローデンバックの短編作品におけるキャリアは、可能性を探る過程である。彼はアニメーション作家のなかで、高畑勲とノーマン・マクラレンをとりわけ好んでいるのだが、それは彼らが、作品ごとに必然性のある手法を選び、ひとつとして同じ作品を作らないからである。
ドキュメンタリー、砂絵、抽象、物語、実験……本作『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』にたどり着くまで、ローデンバックの短編作品群はとにかく多彩な顔を見せており、それは、あまりにも多彩すぎて、同一作家のものには思われないくらいである。実際、短編作家時代のローデンバックは映画祭シーンではそこまで認知度が高くなかった。専門家からしても、ローデンバックのスタイルというものを捕捉することが難しかったというのが、その理由だろう。(アヌシー国際アニメーション映画祭に作品が選出されたのも、本作が初めてのことだった。)
そんなふうにして経歴を重ねてきたローデンバックがたどり着いた初長編『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』は、長編作品としては異例のスタイルをもつものとなっている。長編でありながら作画をすべてひとりでやること……そのこと自体はいまや珍しくなくなった。しかし、人によっては未完成に思えてしまうようなデッサン調の絵柄によって全編が構成され、それでもなお、「実験的」であることが前面には出されず、ある種の大衆性を獲得しているというこの立ち位置は、おそらく前代未聞のものであろう。
本作はカンヌ映画祭でのプレミア上映からスタートして、世界中の映画祭で大きな評価を得ている。フランスでは子供向けにリリースされ、ヒットも飛ばしている。見慣れぬスタイルではあれど、受け入れられているのだ。『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』は、ローデンバックにとって、「長い短編」を作る試みでもあった――短編でしか可能でないはずの実験的で特異なスタイルを長編によって成立させることを試すという意味において。
そんな態度の本作がこれほどまでに世界的な支持を獲得しているのは、この「長い短編」のようなスタイルで作られた長編アニメーションが、世界中で増えつつあるからだ。トム・ムーア(『ブレンダンとケルズの秘密』『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』)、アレ・アブレウ(『父を探して』)、アルベルト・バスケス(『サイコノータス(日本未公開)』)……さらにはウェス・アンダーソンの人形アニメーション作品(『ファンタスティックMr.Fox』『犬ヶ島』)だったり、『この世界の片隅に』の片渕須直、さらには京都アニメーションの山田尚子ら、独自の世界を作り上げるタイプのアニメ作品もその列に含めてもいいかもしれない。これら「長い短編」としての長編作品は、アニメーション産業における既存の定型を否定し、監督=作家のパーソナルなスタイルを全面に押し出しつつも、大衆性を獲得する。これらの作品群が、本作のための着地点を準備したのだ。
ローデンバックはその象徴的な始まりを湯浅政明の初長編『マインド・ゲーム』に見ている。カリカチュアの効いた造形のドローイング、自然主義とは程遠い色使い、臆せず用いられる実写……変化するリアリティに応じて多彩なスタイルを組み合わせる本作は、日本以上に海外で影響力が強く、当時の若い作家たち(=現在活躍する中堅の作家たち)にそのあとを追わせた。『マインド・ゲーム』が何を教えたのかといえば、アニメーションにおいて、ビジュアルのスタイルはどんなものであってもよく、語られるべきものに従って変幻自在となってよい、ということである。それはつまり、ローデンバックが短編においてやってきたことでもある。湯浅政明が『夜明け告げるルーのうた』で世界最大のアヌシー国際アニメーション映画祭にてクリスタル(グランプリ)を獲得するその前年、『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』は審査員賞を受賞している。これら「長い短編」の作品はいまや、世界のアニメーションの新たなスタンダードとなっているのだ。
これら「長い短編」作品たちは、それぞれに必然的なスタイルを見つけ、これまでのアニメーションのあり方にヒビを入れ、新たな景色を見せ、可能性を発掘していく。では、『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』が見出したアニメーションの可能性、その「革新」とはなんだろうか? それは、広い余白と、強固な輪郭もはっきりとした顔立ちも持たない抽象的なキャラクターを活用することで、寓話としてアニメーションを機能させることである。少女、悪魔、王子、庭師、水の精……本作では、誰もが固有名詞の名前を持たない。「クリプトキノグラフィー」を随所に用いながら走るように描かれた筆絵のアニメーションは、動的に姿を変容させ、とらえどころがない。少女は主人公であるにもかかわらず、顔がはっきりしない。作品は全体として、曖昧で流動的な印象を持ったままに揺れ動くのだ。
その「曖昧さ」は何をもたらすのか? ローデンバックは本作の日本公開のために二度来日し、様々な媒体からの取材を受けたが、そこで日本人の記者から「少女が東洋人に見える」という指摘を受けるたび、苦笑していた。なぜなら、彼にとっては、少女はブロンドの白人だったからだ。これが意味するのは、造形上の失敗ではない。抽象度の高いビジュアルが、作品を観る人によって、それぞれ違ったイメージとして読み取ることを許容する、ということである。
観る人によって印象を変える、その揺らめき動きつづける感覚こそが、本作には必要だった。ローデンバックはグリム童話の原作「手なし娘」に、今でも通用するような普遍性を見出した。少女の辿る道、王子の成長、父親の葛藤といったものすべてに、自らの人生のどこかしらの部分を読み込んだ。おそらく、観客である私たちもまたそうだろう。画面のなかでうごめくイメージが、まるでロールシャッハテストのように、自分の人生を映す動的な鏡として、何かを読み込ませる。そして、感情を強く、深く揺さぶる。普段名前をつけることができないあの気持の揺れがイメージとシンクロする。何も確かなものを示さないがゆえに、無限に複雑で機微に富んだ感情を、本作のアニメーションは、豊かな井戸のように汲み取りつづけることを許す。
そのような作品のあり方にとってのキーワードとして、ローデンバックは「謎」という言葉を挙げる。それは、解釈にブレがなく、ひと目で見てわかる、一般的なアニメーションのあり方とは大きく異なる。フランスで本作は子供向けにリリースされたが、しかし本作は「子供にかしづく」ようなものではないという。「子供だからこれくらいでいいだろう」というものでもない。子供が見たこともない世界に背伸びをして、それによって何かを未知なるものを読み込めるものにしているのだという。本作は謎を謎のままに残す。そこから何を受け取るべきなのか、何を見出すべきなのか、本作は明確な答えを用意しない。その答えはあくまで、自分で見出すしかない。答え合わせもできない。だから、本作を観ることは、まるで冒険のようでもある。筆者が本作を初めて観たとき、とても勇敢な作品だと思った。誰も作ったことがないような表現を、長編アニメーションという場で臆することなく行う、まったくブレるところのない作品に見えたからだ。私は自分の道を行き、曖昧で流動的な未踏の領域を切り開いていくが、きっとその場所から、あなたもなにかを汲み取るだろう?という、観客に対する信頼を感じたからだ。
少女は常に移動する。最初はやむなき事情だったが、最後には自分の意志で、未踏の地へと飛び立つことを選ぶ。本作を観るとき、この変化の過程を、観客もまた体験するはずだ。未踏の表現が見せる、誰もまだ確かな答えを持たない「野生の」場所への飛翔。他の数多くの「革新」たちとともに、本作はアニメーションの野生を切り開く。そして、その先に、自分だけの場所を探すことを促すのだ。



| 地域 | 劇場名 | 電話番号 | 公開日 |
| 東京 | ユーロスペース | 03-3461-0211 | 上映終了 |
| 東京 | 下北沢トリウッド | 03-3414-0433 | 上映終了 |
| 東京 | ユジク阿佐ヶ谷 | 03-5327-3725 | 上映終了 |
| 東京 | 新文芸坐 | 03-3971-9422 | 3/7 |
| 横浜 | シネマジャック&ベティ | 045-243-9800 | 上映終了 |
| 川崎 | 川崎市アートセンター | 044-955-0107 | 上映終了 |
| 上田 | 上田映劇 | 0268-22-0269 | 上映終了 |
| 高崎 | シネマテークたかさき | 027-325-1744 | 上映終了 |
| 札幌 | シアターキノ | 011-231-9355 | 上映終了 |
| 名古屋 | 名古屋シネマテーク | 052-733-3959 | 上映終了 |
| 名古屋 | キノシタホール | 052-731-3819 | 上映終了 |
| 金沢 | 金沢シネモンド | 076-220-5007 | 上映終了 |
| 大阪 | シネ・リーブル梅田 | 06-6440-5930 | 上映終了 |
| 大阪 | シネ・ヌーヴォX | 06-6582-1416 | 上映終了 |
| 京都 | 京都シネマ | 075-353-4723 | 上映終了 |
| 京都 | 出町座 | 075-203-9862 | 上映終了 |
| 神戸 | 元町映画館 | 078-366-2636 | 上映終了 |
| 岡山 | シネマ・クレール | 086-231-0019 | 上映終了 |
| 広島 | 横川シネマ | 082-231-1001 | 上映終了 |
| 山口 | 山口情報芸術センター | 083-901-2222 | 上映終了 |
| 福岡 | KBCシネマ | 092-751-4268 | 上映終了 |
| 熊本 | Denkikan | 096-352-2121 | 上映終了 |
| 大分 | シネマ5 | 097-536-4512 | 上映終了 |
| 鹿児島 | ガーデンズシネマ | 099-222-8746 | 上映終了 |

チラシの画像はこちらからダウンロードできます。
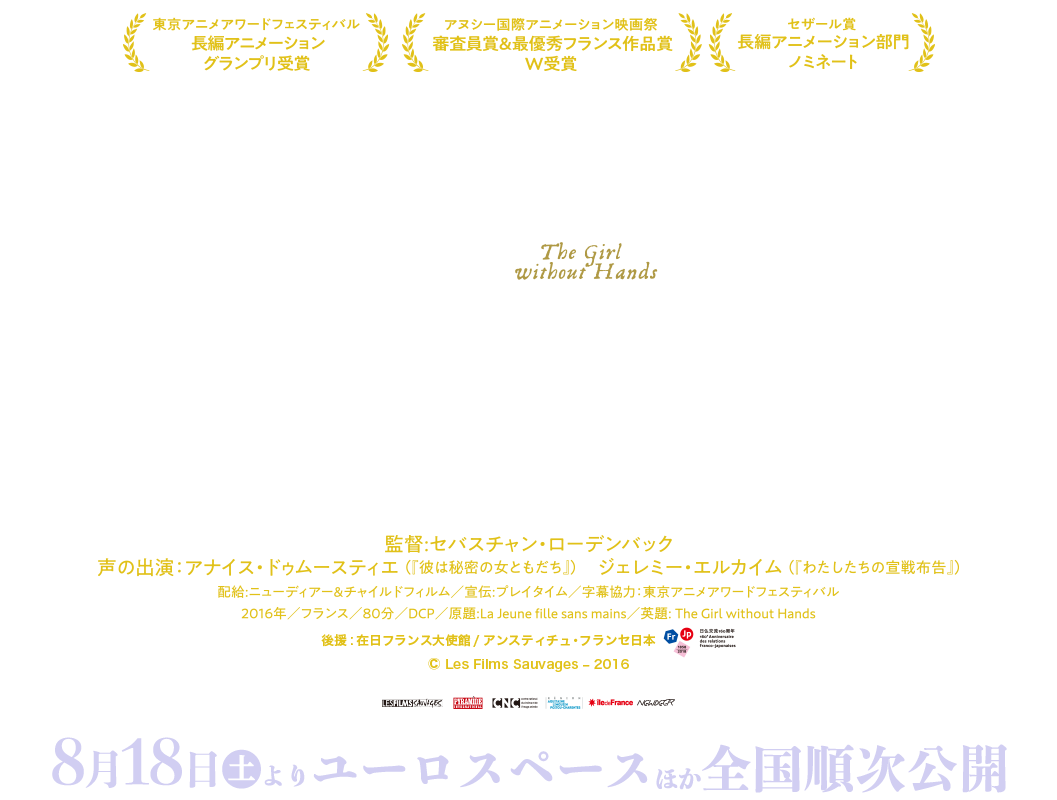


































ここにあるのは映画だ。重厚で凄まじい一本の映画だ。
駒の間での線の欠落と補填、削ぎ落とした要素で成立させた画面は、見ることへの興味を沸き立たせる。
アニメーション描画における省略の可能性の追求という点でとても共感している。
残酷さと優しさが混ざり合う世界の中を泳ぐかのような「体験」でした。
ふっと息を吹きかけただけで崩れてしまいそうな物語にその「声」が与える「強さ」は少女がずっと手放さずにいるそれそのものだ。